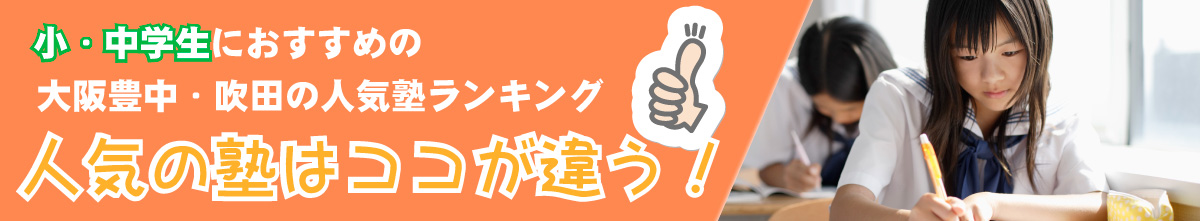他の本来的な勉強道具のポイント①
【バッグ】
手持ちのかばんは「丈夫な素材で軽量、そしてたくさん入るもの」を使いましょう。
私は昔なんとなくデザインが気に入ったという理由だけで「ダレス・バッグ」を使用していましたが、これは相当重量があって、機能的ではないように思いました。
(弁護士らしさを強調するのには良いかもしれませんが)今はたいてい薄くてしっかりしていて、鞄の中もしっかり整頓できるアラミスの安売りを使っていますが、大変便利です。
私は以前受験生だったころも素材のしっかりした軽量バッグを使用して塾に行っていましたが、これは大変重宝しました。
持ち物が沢山ある時もしっかりと詰め込みができ、バッグそのものは重くないので長い時間持っていても疲れないのです。
大事な点は順番に
①バッグの重量
②丈夫さ
③持ち物を全て入れても空きスペースがあること
④鞄の内ポケットが便利なものかどうか
⑤デザイン性
などになります。
もちろん自動車や原付などでいつも移動が可能な人はバッグが重くても構わないのでしょうが。
【ラインマーカー】
ラインマーカーはどこの文房具屋でも販売している一番人気のあるものを使用されるとよいでしょう。
「簡単に手に入るものに固執しましょう」ということです。
ちなみに私は三菱鉛筆の太文字細文字の両方が書けるラインマーカーを使用しています。
どうして「手に入りやすい物」に拘るのかというと、勉強中にきれてしまったとき(外出先などで)同一のものが手に入りやすいととても便利だからです。
文具メーカーによってラインマーカーの色が微妙に違います。
そのため、参考書に「色分け」(あとで書きますが、これはとても便利な技術です)している途中で他のメーカーのラインマーカーに使いかえると
後に、何回も参考書を読み返すときに落ち着かないかんじがしたり、下手をすると他の色と識別を間違ってしまう可能性もあります。
そうなってしまうとせっかく色分けしたのに何にもならないのです。
直接目に入って来るラインマーカーの色には細やかな気配りをしましょう。
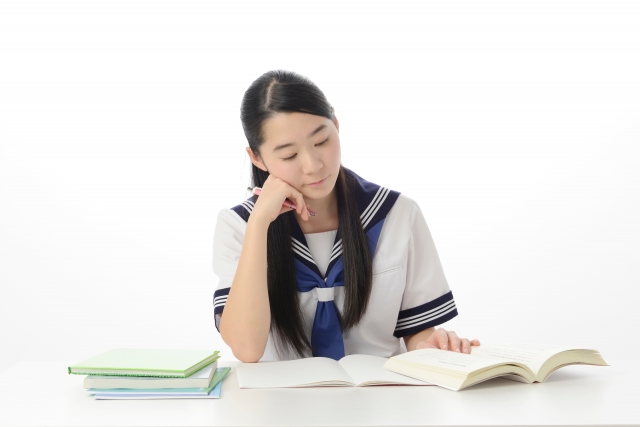
【ノート】
私はノートをメモのようにしか使用していません。
それは大事なことは基本的に全て参考書(基準書)にびっしり書き残すからです。
今はノートとしてロディア製メモパッドのB5サイズを使用しています。
これはファイリング・ノートのように重量がなく。
好みのところをきれいに切り取って使用できるという点がとても便利だからです。
「ノートにメモを残す」から「メモの大事なところを基準書に書き残す」までのおおまかな工程はまず授業でノートをとる、復習する際に、ノートに記述した中身のうち大切なところを参考書に全部書き残すーという形になります。
つまりノートはあくまでも基準書に書き写すまでの「繋ぎ」でしかありません。
ですから、ノートは「使いやすさ」を追求して選択するべきです。
またノートから基準書に活気写しが出来ず、やむを得ずノートのページをそのまま切り取って貼り付けなければならないこともあります。
そのようなとき、私は同様にロディア製のメモ帳サイズのノートを使用していますが、貼り付けをしなければいけないほどの大容量の内容はそれほどありません。
念のためにノートをもっているというくらいのものです。
尚、貼り付けるために大き目の付箋を使用している人がいますが、急場をしのぐための利用であればともかく参考書に補足を加えるために添付するのであれば、あまりそれはよくありません。
何故かというと付箋は剥がれやすいので失くしやすく、他のところにくっついてしまったり、ごちゃごちゃになってしまうことがよくあるからです。
吹田の塾生にもいました。
付箋はあくまで忘れないための一時しのぎ、またはすぐに必要ページを開くための道具として利用するべきでしょう。
前回の記事はコチラ→【効率的に勉強をする為の道具とは?】